書評:「絶望死のアメリカ」
アン・ケース/アンガス・ディートン みすず書房2021年
「トランプ現象」の根底にあるもの
西島志朗
「絶望死」のエピデミック
アメリカ労働者階級の中の、特定の社会的属性を持つ労働者の平均寿命(出生時平均余命)が短くなっている。短命化しているのは、「非ヒスパニック系白人」(ルーツがスペイン語圏ではない白人)
(注1)で、大卒の学位を持たない中年の労働者層である。
最も増えている死因は、「自殺」「薬物の過剰摂取」「アルコール性肝疾患」で、著者たちはこれらをまとめて「絶望死」と呼ぶ。「2017年、15万8千人のアメリカ人が・・・絶望死で命を失った。これは、ボーイング737MAX機が毎日3機墜落して、乗員乗客が全員死亡するのと同じ数字だ」(P99)。この「絶望死」による死者は、1990年代から一貫して、右肩上がりで増え続けている。航空機の墜落事故がこんなに頻繁に発生すれば、社会は大パニックになるだろうが、「絶望死」は社会の表面には出てこない。それは深く潜行したまま拡大し、アメリカ社会を蝕んでいる。
「貧困」だけでは説明できない
2人の著者は、学歴、人種、性別、居住地域、収入、社会保障、医療など様々な角度から、「絶望死」の増加状況を詳細に調査し、この現象を「エピデミック」(注2)だと結論付ける。そして、この現象の真の原因を突き詰めていく。誠実で徹底的に実証的な2人の著者の論考は、「トランプ現象」の背景にある経済社会の変化を明らかにすることに成功している。
2人の著者は、「絶望死」の増加の原因を「貧困」に還元することに同意しない。「貧困」が主要な原因であれば、黒人層の下層労働者の方が、大きな影響を受けるだろうし、実際に、「貧困層」の増減と、90年代以降一貫して増大し続ける「非ヒスパニック系白人」の「絶望死」のグラフは全く一致しない。
「・・・私たちは貧困や大不況[リーマンショック後の不況のこと]が絶望死の急増という本書の物語にとって中心的な役割を果たすとは考えていない」「何が絶望死を引き起こしているのかと聞いたときに返ってくる答えは、貧困、不平等、金融危機、もしくはその全てであることが多い・・・たしかにどれも重要だが、どれひとつとして、絶望死の主な原因ではない」「生活水準のさまざまな指標は白人よりも黒人の方が悪いのだが、1990年代から2013年にかけて、絶望死によって死んでいたのはほとんどが白人だった。非ヒスパニック白人にだけ影響していたのが何だったにせよ、ほかの集団よりも貧しいことが理由ではなかったのは確かだ」(P146~148)。
「フードスタンプ」に頼らざるをえない貧困が拡大し、いまや米国では9人に1人、つまり約3800万人が生活必需品にも事欠く貧困状態にある。リーマンショック後の住宅の差し押さえは400万件を超えた。金融危機の2年間で、のべ5280万人が一時解雇(レイオフ)の対象となり、約860万人が職を失った。200万人以上が水道や水洗トイレを持たない。2007年に80万人弱だったホームレスの子供は18年には約130万人に増えた。メキシコ経由で輸入されるフェンタニルなどの致死的な麻薬が拡大している。
「絶望死」が増加する要因として、これだけあれば「もうたくさんだ」と言いたくなる。しかし、2人の著者は、「それだけでは説明できない」という。2人が到達した結論は、利潤の最大化をめざすアメリカ資本の運動、1970年代以降本格化した「資本のグローバル化」と「生産現場の技術革新」の帰結に重なる。
「高級ブルーカラー階級」の崩壊
著者たちがたどりついた結論は、どういうものなのか。少し長いが引用する。
「1970年代以降のアメリカ経済では多くの仕事が存在しなくなってしまった。その中にはゼネラルモーターズ・・・やベツレヘムスチールなどの工場のように、給料が良いものも多かった。男たちは父親に倣って、・・・組合がある給料がいい製造業に就き、中流階級生活を構築できるだけの金を稼ぎ、マイホームを持ち、いい学校に通う子どもたちを育て、定期的にバカンスを楽しんでいた。彼らは高級ブルーカラー階級という、いかにもな名で呼ばれた。だがそうした仕事の多くはなくなってしまった。1950万という史上最高記録を叩き出した1979年から、大不況前年の2007年の間に、500万以上の仕事が失われ、1380万まで減ってしまった。製造業は金融危機の際に大打撃を受け、さらに200万の仕事が失われる・・・こうした雇用は海外からの輸入、工場の自動化、グローバル化、ロボット化、に取って代わられてしまった」(P175)。
「アメリカの労働者階級は常に存在したわけではない、労働者階級を支え、定義したのは製造業だ。製造業は19世紀に農業から工場へと労働者を奪っていき、その勢いは南北戦争後に加速し、1950年頃ピークを迎えた。専業主婦の増加は、1950年でもまだ比較的新しい現象だった。それまでは夫と妻が協力して生計を立てるものだった。しかし男は工場で働くようになり給与明細額よりも難しく生産的な労働の尊厳に意義を見出すようになった。・・・製造業とそこから生じた労働者階級の暮らしは、男と女の役割、そして家族の暮らしがどうあるべきかを定義した。製造業の台頭は新たな暮らしの形を生み、仕事と人生の新たな意義の見出し方をもたらした。組合加盟がピークに達したのもこの頃だ。・・・[組合は]組合員の賃金を引き上げ・・・職場における健康と安全を監視した。組合によって労働者は一定の民主的コントロールを獲得し、それは職場にとどまらずより広い範囲に及んだため、地域社交生活の重要な部分となることが多かった。アメリカの労働組合が1950年代初頭にピークに達した頃には、労働人口の33%が組合員だった。2018年の数字は10・5%で、民間企業の従業員で組合に属していたのはわずか6・4%だった。製造業が露と消えると、労働者たちはあまり望ましくない、簡単な仕事に移らざるを得なくなっていった。その多くがサービス業で、医療、飲食、清掃、警備といった業種が多く、製造業の仕事は少なかった。サービス業の仕事の多くは望んだものではなかった。個人の成長や生産性の伸びがほとんど期待できなかったり、言われたことをそのまま、言われたその時にやらなければならなかったりする仕事だ。個人がイニシアティブをとる余地かない。そうした仕事に就く労働者は事実上ロボットが来るまでのつなぎに過ぎず、プログラマーたちがロボットに仕事を教えられるようになるまでの存在だった」(178-179)
「アメリカの白人労働者階級の崩壊にはもう一つ別の側面がある。多くの地域、多くの企業でそれは白人労働者階級だった。アフリカ系アメリカ人ではそうではなかった。白人は黒人に対する特権を有し、その特権は長年続いた。だが特権は縮小また消失した。社会学者アンドリュー・チェルリンによれば、『ブルーカラーの労働者のための広い機会が制限されていく環境にあって、白人労働者は黒人の伸長を、自分が持っていた人種的特権地位の弱体化ではなく、機会の不平等な剥奪とみなしている』。ピュー研究所の調査によれば、アメリカの白人労働者階級の50%以上が、黒人やその他のマイノリティに対する差別と同じぐらい、白人に対する差別が大きな問題になってきていると考えている。・・・仕事世界と仕事世界が生み出し支えていた家族生活の両者が、同時に失われた。そして人種的特権が失われたと考えられればまだましで、逆差別すら起こっているとみなされるようになっている。この両者の組み合わせは有害で・・・所得減少よりも強力なのだ」(P180-181)。
雇用と労働の劣化はさらに進む
「非ヒスパニック系白人」に属する学位を持たない中年労働者の間で増加する「絶望死」の背景には、崩壊する製造業労働者階級(高級ブルーカラー)の長い物語がある。単に、職場を失って望まない職種と低賃金に苦しめられているだけではない。彼らが失ったのは、熟練の技能を発揮する場所であり、労働組合であり、地域のコミュニティであり、労働過程での裁量権であり、労働者としての誇りであり、労働と人生の意味である。
デトロイトの自動車工場の跡地にアマゾンの物流倉庫が作られ、賃金は半分になった。アマゾンは、「正社員」を「非正規」に置き換えて低賃金を強制し、ロボットを導入し、現場労働者をロボットの補助作業員としてコンピュータの「アルゴリズム」に従属させる。労働者の本当の敵はアマゾンだ。しかし、トランプの関税政策を熱狂的に支持する労働者は、敵はトヨタやフォルクスワーゲンだと信じている。トランプの保護貿易政策は、国内の階級対立の先鋭化に対する対策でもある。一昨年、40%の賃上げを求めてストライキ闘争を闘ったUAWのシェイン会長は、トランプ関税を支持すると言っている。経営と労働者の対決ではなく、「自国の産業を守る」という「共通利益」のために資本と労働者が協力する姿・・・。これだけで、トランプを担ぎ出したアメリカブルジョアジーの狙いは半ば成功していると言いうる。
雇用と労働の劣化は、2人の著者が描いた状況のさらに先へ進んでいる。AIの開発と実装は、高賃金のホワイトカラー層を削減するだけでなく、生産とサービスの現場でさらに労働者を削減し、「アルゴリズム」への従属を徹底する。「ギグワーク」、「スポットワーク」、「クラウドワーク」、「デジタル内職」などが一般化し、労働力の構成は抜本的に再編成されつつある。それは、労働者をますます「アトム化」し、「労働と人生の意味」を喪失させる「長い物語」の続編になるのだろうか。
労働運動は、AIの開発と実装に反対し、雇用と労働の劣化に抗して、新たな「コミュニティ」の形成を視野に入れなければならない。
4月15日
(注1)「米国勢調査局は12日、2020年国勢調査の詳細結果を発表した。ヒスパニック(中南米系)を除く白人の人口が10年から2~6%減少した。ワシントン・ポスト紙など米メディアによると、白人人口が減少したのは1790年の調査開始以来初めて。全人口に占める割合も57・8%となり、初めて6割を切った」(読売新聞2021年8月13日)。
(注2)世界保健機関の定義によると、「エピデミック」とは、「明らかに正常な数値を超えた症例が地域や社会で発生していること」を指す。「パンデミック」は世界的大流行のことを指し、「エピデミック」とは区別されている。
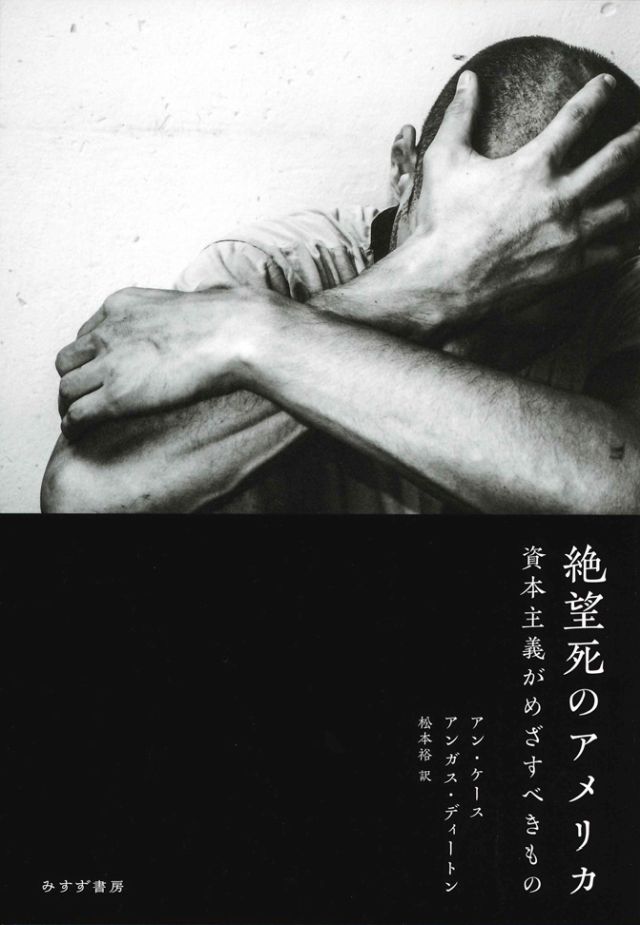
週刊かけはし
《開封》1部:3ヶ月5,064円、6ヶ月 10,128円 ※3部以上は送料当社負担
《密封》1部:3ヶ月6,088円
《手渡》1部:1ヶ月 1,520円、3ヶ月 4,560円
《購読料・新時代社直送》
振替口座 00860-4-156009 新時代社


